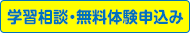入試に役立つ理科実験「溶解と再結晶」
こんにちは。理科実験教室を担当している望月です。
水に物質が溶けることを「溶解」といいます。
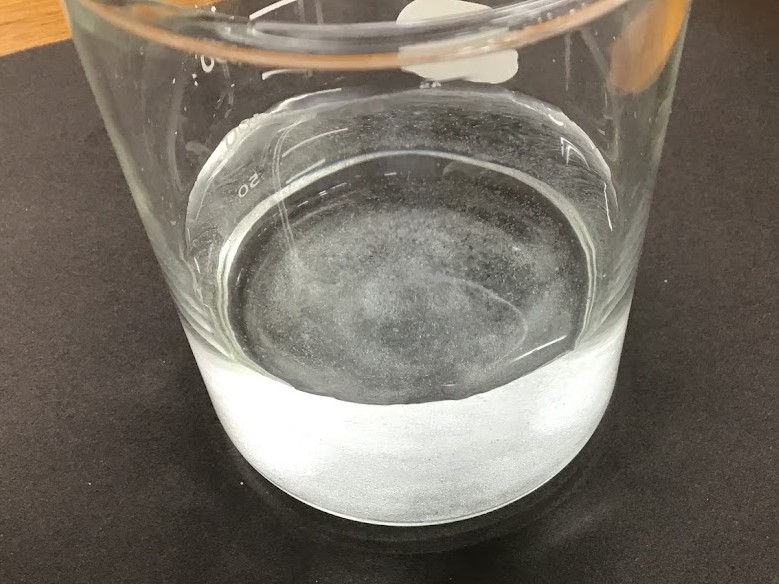
しかし、どんどん溶かしていくと、溶け残りがでてきます。
これは溶ける「限度」があるからです。
一定の量(100g)の水に溶かすことができる限度の量をその物質の「溶解度」といいます。
これは決まった量で、物質により違います。
・水に溶けやすい物質
・水に溶けにくい物質
があるのは、そのためです。
溶け残ったらどうすればよいのでしょう?
・加熱して温度を上げる。
こう思い浮かべる人が多いですね!
そのとおりで、実は、溶解度は水の温度によって変わるのです。
さきほどの溶け残ったものを加熱すると、
下の写真のように溶けてしまいました。

このまま置いておくとどうなるでしょう?
水溶液の温度は、置いておくと下がってきますね。
ゆっくり冷えていくと、中に何かでてきます。
出てきたものを取り出してみると、
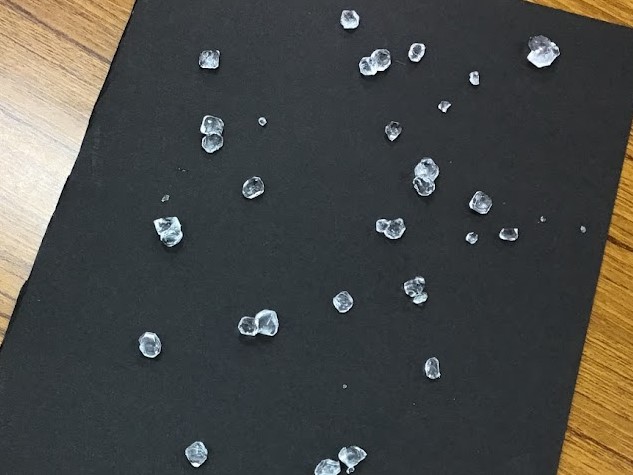
元の粉ではなく、かたまりとしてでてきます。
こうして出てきた、物質によって決まった形のかたまりを、「結晶」といい、
一度温度を上げて溶かしたあと、冷やして結晶を取り出す方法を「再結晶」といいます。
ゆっくり冷やすと、大きな結晶ができるので、
写真のようになるのですね!