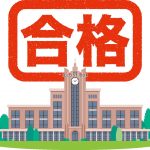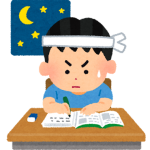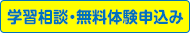共通テストお疲れ様でした!――「理科②生物」所感
慶林館大分セントポルタ校高校部の山﨑です。
1月16日(土)・17日(日)、「大学入学共通テスト」が実施されました。
今年度は感染症対策のため、会場に赴いての激励は控えましたが
慶林館講師一同、受験生の健闘を祈っておりました。
無事に2日間の試験を終えられて、ひとまずは肩の荷が下りた心地かと思います。
これから先は、私立大学入試や国公立大学2次試験の本番が待っています。
受験生は気を抜かず、よりいっそうの緊張感をもって、勉強に取り組みましょう。
さて、今年度が第一回となる「大学入学共通テスト」は、各科目において
従来の「センター試験」と傾向のちがう部分も多くありました。
今回は「理科②」の「生物」を例に挙げて見ていきましょう。
「生物」の大きな変更点としては、大問6題のうち
「選択問題が無くなり、必答問題のみになった」ことが挙げられます。
問題の総数は、ほぼ昨年度と変わっていませんが
「新傾向の問題」が入ってきたこともあり、問題文や図表をしっかりと読み込む必要があるために
時間が足りないと感じる受験生は多かったかもしれません。
第3問では「会話文を読んで答える問題」、第5問Bでは「実験を踏まえて試行錯誤する問題」が出題されました。
第1問は「代謝・遺伝子発現・進化」など複数の単元に関わる内容を問われる形でした。
全体として、「知識を問う問題」が減少し、「実験から考察する問題」が増加した印象です。
各単元の知識を踏まえてきちんと内容を読み取れたならば、問題としては例年並みの難易度だった思います。
これから共通テストに向けて勉強していく新高校2・3年生は
今まで習った知識を定着させるために、まずは教科書内容をしっかりと復習しておきましょう。
共通テストではどの単元も大事です。苦手な単元があれば足を引っ張られます。
また、定期テストや模試で扱われた問題のひとつひとつを、満点がとれるくらい完璧にやり直しましょう。
生物ならば「何を調べるためにこの実験をするのか」「なぜこの実験方法が選んだのか」
「なぜこの実験はこんな結果になったのか」「この実験結果からどんなことが読み取れるのか」が分かるまで
解説を読み込み、分からない所は何度も質問しましょう。
教科書などで見覚えのある問題がそのまま出題されることは稀です。
どんな問題にも対応できるようにしていきましょう。