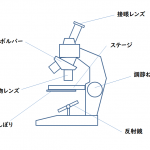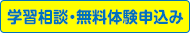入試に役立つ理科実験「温度」
こんにちは。理科実験教室を担当している望月です。
今回は、入試によく出る「温度」についてです。
みなさんは、「温度」についてたずねられたらなんと答えますか?
「温度計ではかる」
「温めると上がる」とか?

たとえば、写真のようにカイロで温度計を温めると、
赤い液がどんどん上がっていって、みなさんは
「・・・度になった」とこたえますね。
単位としてつく「℃」。
これを「摂氏(せっし)」といいます。
正確には摂氏度・セルシウス度といい、
昔の科学者アンデルス・セルシウスという、
初めて実用温度計をつくった人の名前からきているそうです。
摂氏度は、
水が凍る温度を「0度」水の沸点を「100度」とし、
そのあいだを100で分割した一つを1度としています。
摂(セルシウスの頭文字を漢字で表したもの)氏(人の名前につける)という
ことで、人の名前なんですね。
「水の状態変化」を基準にして温度計がつくられている、
というのは、
水の惑星である「地球」らしいとおもいませんか。
※アメリカでは「華氏(℉)」がつかわれています。
たとえば摂氏20度は、華氏68度です。興味がある人は調べてみてください。